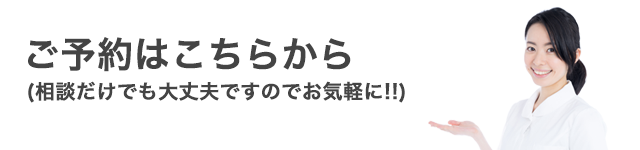嗅覚障害とは?
私たちは食事や季節の移ろい、危険を察知する際にも「におい」を感じ取って暮らしています。
この嗅覚が低下したり失われたりする状態を嗅覚障害と呼びます。
医学的には以下のように分類されます。
•嗅覚低下 … 匂いが弱くなる
•嗅覚消失(無嗅覚) … 匂いがまったくわからなくなる
•異嗅症 … ないはずの匂いを感じたり、匂いが変に感じたりする
コロナウイルス感染後や副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、頭部外傷、加齢などが主な原因です。
東洋医学の考え方
東洋医学では、鼻は「肺」と「脾(消化器系)」の働きと深く関わるとされます。
肺の気が滞ったり、脾が弱って湿気が体に溜まると、鼻の通りが悪くなり、においがわかりにくくなると考えられます。
治療では、肺や脾の気を補い、気血の巡りを改善するツボ(迎香、印堂、合谷、足三里 など)を用います。
嗅覚障害で感じ取りやすい匂いは?
興味深いことに、嗅覚障害の人でも強い刺激臭や特定のガス臭(アンモニア、酢酸、揮発性の酸など)は比較的感じやすい傾向があります。
これは嗅細胞ではなく、**三叉神経(痛みや刺激を感じる神経)**が刺激されるからです。
例えば、
•アンモニア
•酢(お酢の匂い)
•唐辛子やわさびの刺激
•煙や刺激性ガス
などは、においというより「ツーンとする感覚」でわかる場合が多いです。
逆に、バラやバニラなどの甘い香り、繊細な香水の匂いは、嗅細胞でしか感知できないので、障害があると感じにくくなります。
嗅覚は日常の豊かさや安全にも直結する大切な感覚です。
もし「においがしない」「変なにおいがする」と感じたら、耳鼻科で相談することが大切です。
また、東洋医学的な体質改善や鍼灸もサポートになります。
お気軽にご相談ください。