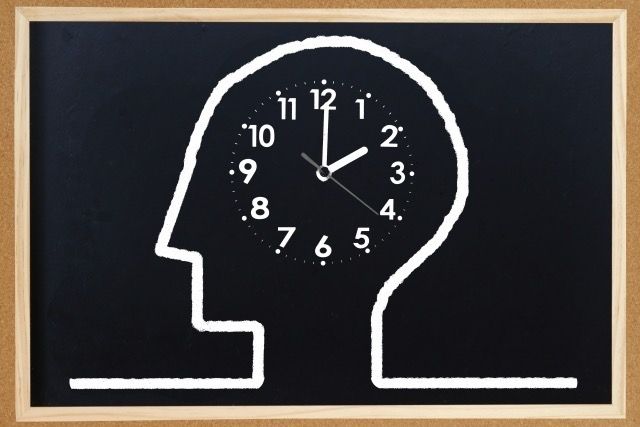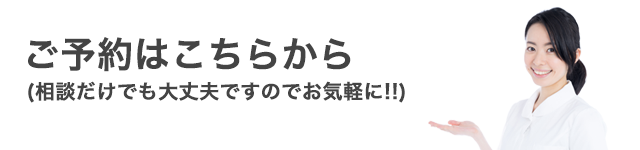自律神経は、私たちの体が意識しなくても自動的に働いてくれる神経系のことです。
逆に言うと、私たちの意思で動かそうとしてもコントロールできないということでもあります。
自律神経の基本的な役割
自律神経の主な役割は、生命を維持するために必要な体の機能をコントロールすることです。
具体的には、以下のような働きを調整しています。
・呼吸: 息を吸ったり吐いたりするリズム
・心臓: ドキドキと血液を全身に送るポンプ機能
・消化: 食べ物を分解し、栄養を吸収する働き
・体温: 暑いときには汗をかき、寒いときには震えることで体温を一定に保つ機能
・血圧: 血管を収縮・拡張させて適切な血圧を維持する機能
・排泄: 不要なものを体の外へ出す機能
・免疫: 病原体から体を守る機能
・ホルモン分泌: 体の様々な機能を調節するホルモンの分泌
これらの機能は、私たちが「意識して!」と命令しなくても、自律神経が勝手に調整してくれています。
例えば、運動中に心臓がドキドキするのは「もっと酸素が必要だ!」という体の要求を自律神経が感知し、心臓に「もっと頑張って!」と指令を出しているからです。
自律神経の2つのモード:交感神経と副交感神経
自律神経には、主に交感神経と副交感神経という、まるでアクセルとブレーキのような、反対の働きを持つ2つの神経があります。
交感神経
主に活動している時や、ストレスを感じている時に活発になります。
体を「戦闘モード」や「逃走モード」にするイメージです。
・心拍数を上げ、呼吸を速くし、血管を収縮させて血圧を上げます。
・筋肉への血流を増やし、瞳孔を開いて視覚を鋭敏にします。
・消化活動は抑制されます。
・例えるなら、「昼間の活動モード」や「緊急事態対応モード」です。
副交感神経
主にリラックスしている時や、休息している時に活発になります。
体を「休息モード」や「回復モード」にするイメージです。
・心拍数をゆっくりにし、呼吸を穏やかにし、血管を拡張させて血圧を下げます。
・消化活動を活発にし、エネルギーを蓄えます。
・例えるなら、「夜間の休息モード」や「リラックスモード」です。
これらの2つの神経は、シーソーのようにバランスを取りながら、私たちの体の状態を常に最適な状態に保とうと働いています。
自律神経の根本
人間を含め動物は狩猟や採集により生存してきました。
現代のように電気のない時代には、日が登ると狩へ出かけ、天敵が現れたら戦うか、逃げるかを即座に判断して身体が反応しなくては生き残れない環境でした。
日が沈むとその間に身体を休め、次の狩への体力を温存していたでしょう。
このように、身体には活動と休息のスイッチが備わっているわけです。
敵が目の前に現れた時、戦うにしても逃げるにしても筋肉が収縮して動けるよう、交感神経が興奮します。
怪我をした時に出血を最小限にとどめるために血管は収縮しますが、全身に血液を送る必要があるため、心拍数と血圧は上昇します。
視覚での情報を収集するために瞳孔は開き、たくさんの酸素を取り入れるために気管支は開いて呼吸が早くなります。
危機的状況では消化管である胃や腸は活動をおさえ、食欲や排泄への意識はなくなります。
日が沈む頃には安全な場所で身体を休ませるため、筋肉の緊張は解け、血管が拡張し緩やかに全身へ血液を送ります。
筋肉を休ませている間に、内臓へ血液をまわし栄養するため、消化活動や排泄が活発になります。
このように、自律神経の働きは動物が生存するためにとても重要な働きをしています。
自律神経の乱れとは?
この交感神経と副交感神経のバランスが崩れてしまうと、様々な体の不調が現れることがあります。これが「自律神経の乱れ」と呼ばれる状態です。
自律神経が乱れる原因は様々ですが、主なものとしては以下のようなものが挙げられます。
・ストレス: 精神的なストレスだけでなく、過労や睡眠不足、不規則な生活なども体にとっては大きなストレスになります。
・生活習慣の乱れ: 食事、睡眠、運動などの生活習慣の乱れは、自律神経の働きに悪影響を与えます。
・ホルモンバランスの乱れ: 更年期や月経周期など、ホルモンバランスの変化は自律神経に影響を与えることがあります。
・加齢: 年齢とともに自律神経の機能も徐々に低下することがあります。
・環境の変化: 気温や気圧の急激な変化なども、自律神経の負担になることがあります。
見落とされがちな原因
乱れる原因として見落とされがちですが、交感神経と副交感神経の急激なスイッチングに注意してください。
動く!休む!とメリハリをつけているつもりでも、その切り替えがなだらかでなくオンかオフで切り替えている場合、活動中はそれなりに動けていても、休日になると倦怠感が強くなり、意欲がなく、動けずに1日が終わってしまう…など、心当たりはありませんか?
交感神経と副交感神経はなだらかに切り替えることがとても重要です。
夜中の暗闇から日が登り徐々に明るくなり、日中を過ぎ夕方から夜にかけて徐々に暗く静かになるようにグラデーションで切り替わることが自律神経の本来のリズムです。
寝起きから急いで準備したり、寝る直前まで思考を働かせていませんか?
交感神経が一気にオンになり、就寝の瞬間まで働き続けるため、副交感神経が隙をついて働きだすようになり、急で強い倦怠感が現れているのかもしれません。
自律神経の乱れによっておこる主な症状
自律神経の乱れによって現れる症状は多岐にわたり、人によって現れ方も異なります。主な症状としては以下のようなものがあります。
[精神的な症状]
・ 不安、イライラ
・気分の落ち込み、憂鬱
・集中力の低下
・不眠
[身体的な症状]
・動悸、息切れ
・めまい、立ちくらみ
・頭痛
・肩こり、首こり
・倦怠感、疲労感
・手足の冷え、ほてり
・消化不良、便秘、下痢
・多汗
・口の渇き
・耳鳴り
これらの症状が複数現れる場合や、長期間続く場合は、自律神経の乱れが疑われます。
自律神経を整えるためにできること
自律神経のバランスを整えるためには、日々の生活習慣を見直すことが大切です。
・質の高い睡眠
毎日同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保しましょう。寝る前のカフェインやアルコールは避け、リラックスできる環境を整えましょう。
・バランスの取れた食事
栄養バランスの偏った食事は、体の機能低下につながり、自律神経の乱れを引き起こしやすくなります。規則正しく、様々な食材をバランス良く摂るように心がけましょう。
・適度な運動
ウォーキングやストレッチなどの軽い運動は、血行を促進し、心身のリラックス効果を高めます。無理のない範囲で継続することが大切です。
・ リラックスする時間を作る
意識的にリラックスする時間を作りましょう。深呼吸をしたり、瞑想をしたり、好きな音楽を聴いたり、アロマを焚いたり、自分に合ったリラックス方法を見つけることが大切です。
・ストレスを溜め込まない
ストレスの原因を理解し、適切な対処法を見つけましょう。誰かに相談したり、趣味に没頭したりするのも良いでしょう。
・規則正しい生活
毎日同じ時間に起きて、食事をするなど、規則正しい生活を送ることは、自律神経のリズムを整える上で非常に重要です。
・湯船に浸かる
シャワーだけでなく、ゆっくりと湯船に浸かることで、心身ともにリラックスできます。
まとめ
自律神経は、私たちが生きていく上で欠かせない、非常に重要な神経系です。交感神経と副交感神経がバランスを取りながら働くことで、私たちの体は常に最適な状態に保たれています。
しかし、ストレスや不規則な生活などによってこのバランスが崩れると、様々な不調が現れてしまいます。
日々の生活習慣を見直し、心身ともに健康な状態を保つことが、自律神経を整える上で最も大切です。
もし、自律神経の乱れによると思われる症状が続く場合は、無理せずお気軽にご相談ください。
自律神経は、私たちの健康を陰で支えてくれる大切な存在です。ぜひ、その働きを理解し、労わってあげるように心がけてくださいね。