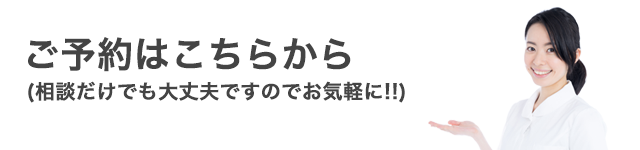症状を強くさせる要因は…
塵埃.化学物質の蒸気.天候.気温.感染.栄養障害.内分泌障害.喫煙.精神的ストレスなどの要因が考えられる。
これらは非特異的間接要因と分類され、自律神経症状にも影響を受けることがある。
症状に直接関係する要因は…
アレルギー性鼻炎の抗原はダニ.ハウスダスト.花粉. 真菌胞子が多い。
アレルギー性鼻炎の病態
抗原が反復して鼻から吸入されると、抗体(Ige抗体)が産生され、鼻粘膜にある肥満細胞やIgE受容体に抗体が吸着する。再び抗原が鼻から吸入されると鼻粘膜に分布する肥満細胞で抗体と結合し、抗原抗体反応が起こる。その結果、ヒスタミンやロイコトリエンという化学伝達物質が遊離する。
ヒスタミンは、神経を刺激してくしゃみを誘発し、副交感神経を介して鼻汁を増加させる。
化学伝達物質は血管の透過性の亢進や静脈の拡張を起こし鼻閉(鼻詰まり)を起こす。
アレルギー性鼻炎を起こしやすい遺伝的な素因もあるといわれている。
症状
発作性や反復性のくしゃみ
水溶性鼻汁や鼻閉(鼻詰まり)
鼻の痒みなど。
随伴症状
睡眠障害.学習障害.集中力の低下.疲労.イライラ感.頭重感.頭痛など。
東洋医学で考える鼻閉.鼻汁の病態
五臓六腑の「肺」は鼻に開竅するため「肺」と鼻は密接な関係にあると言える。
「肺」は宣発.粛降機能があり、正常に働くと気道は清潔に保たれ適度な潤いを保ちます。
*宣発=体内の濁気を排出する.食べた食物から得られる気(水穀の精微)を全身に輸送する.衛気を行きわたらせ発汗を調整する=肺気の宣発が障害されると鼻詰まり.くしゃみ.無汗などの症状が起きる。
*粛降=自然界の清気を吸入する. 食べた食物から得られる気(水穀の精微)を下に下ろす作用.肺を清潔に保つ=肺の粛降が機能しなくなると呼吸が浅くなる.咳や痰.喀血などの症状がおきる。
外感病と内傷病
外感病とは、外から侵入する邪により「肺」の機能である宣発.粛降が失調、固摂の失調などが起こり、鼻閉.鼻汁が生じる。
特徴は、発症が急で経過が短い.悪寒.発熱など。
内傷病とは、慢性の咳で肺気を損傷したり、長引く発熱や脾虚により運化機能の失調により内湿が熱化、肝の疏泄失調により発生した内火が上炎して、鼻閉.鼻汁が生じるなどがある。
特徴は、症状は緩やかで長引く事が多い。
鍼灸治療
アレルギー性鼻炎は鍼灸適応になる。
自律神経のバランスを整え、鼻まわりの血流改善を目的に治療を行う。
治療穴は、印堂穴.迎香穴.上迎香穴などの鼻周囲の刺鍼、手足の経穴などを使う。
また、疲労感が強い場合はリラックスを目的に施術を行う。
日常で気をつける事
①栄養や休養をしっかりとる
油物や甘い物は身体の中に湿熱を生む原因となる為、控える。
バランスの取れた食事と十分な休養をとる。
②アレルゲンに触れないようにする
外から侵入してくる抗原に触れないようにマスクをしたり、特に花粉などが多い日は外出を避けるようにする。
③鼻呼吸を意識する
軽い運動を行う事で肺気が巡り、鼻通りがしやすくなる。普段から鼻で呼吸するように意識する。
④飲酒はほどほどに
過度の飲酒は鼻閉.鼻汁の症状を悪化させる可能性がある為、控える。