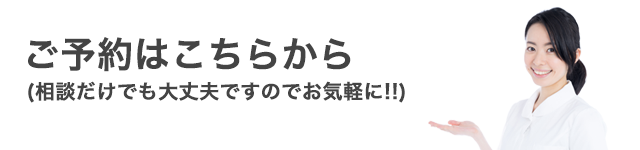原因は…
1.神経因性過活動膀胱
排尿にかかわる神経が原因
脳疾患.脊髄疾患.馬尾末梢神経疾患など
2.非神経因性過活動膀胱
排尿にかかわる神経によらない要因
膀胱血流障害.自律神経の活動亢進.膀胱の加齢.膀胱の炎症など
症状は…
昼間頻尿.夜間頻尿.尿意切迫感.切迫性尿失禁などがある。
重症度評価方法
OABSS(overactive bladder symptom score)
問診時に聴取し、定期的にOABSSを用いて治療効果の効果.判定をする方法がある。
東洋医学での病態
膀胱は、五臓六腑の「腎.膀胱」の気化機能により体内の水分調整や「肝」の疏泄機能(全身に気を巡らす)などによって調整される。
「肺」の宣発.粛降機能(体内な濁気を排出.自然界の清気を吸入)により全身に輸布された津液は「三焦」を通り、各器官に利用されて「腎」に集まる。余分な水液は「腎」の機能により尿に化生され、膀胱に溜まる。
「腎気」の固摂作用により貯尿され、「腎気」の気化作用.推動作用により排尿される。
「腎」の機能失調は、排尿障害の原因になりやすい。
実証
1.膀胱湿熱
熱邪.湿邪が膀胱に停滞し、湿熱となり膀胱の気化機能に失調する。貯尿と排尿を障害する事で排尿障害が起きる。
2.肝鬱気滞
疏泄機能の失調により膀胱の気機が阻滞、尿の排泄に支障が出る。
虚証
1.腎気虚.腎陽虚
加齢や過労などにより腎気の固接作用が低下、腎気不固になると尿を貯尿できず、漏れ出す。
鍼灸治療
過活動膀胱(尿意切迫感.頻尿)は鍼灸適用疾患。
五臓六腑の「膀胱」の機能を改善させる。
「膀胱」の病証は実証である事が多いので気機調節を目的に太陽膀胱経.厥陰肝経などの経穴を瀉法で治療を行う。
生活習慣の見直し
1.肥満があれば改善
BMI30以上は過活動膀胱のリスクが高い。
減量により症状の改善を目指す。
2.禁煙
喫煙は尿失禁のリスク増大の可能性があり。
3.カフェインを控える
カフェインは利尿作用があり尿量を増加させる。
4.冷やさない
寒冷刺激は尿意を誘発させる事がある。
5.休養と睡眠
虚証の排尿障害は過労などで悪化しやすい。
6.ストレスケア
肝鬱気滞などの実証はストレスなどの刺激により症状は増悪しやすい。
適度な運動や自身のストレス発散方法を見つける。