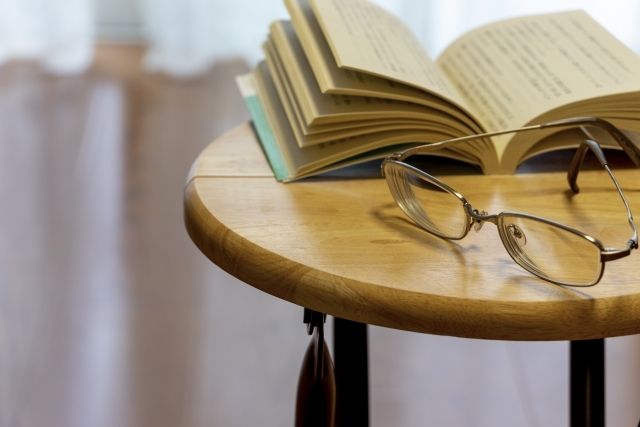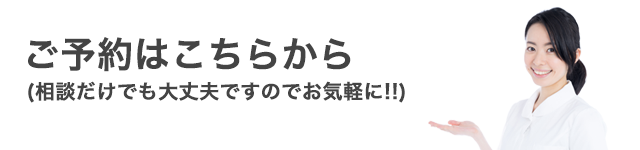動眼神経の作用
動眼神経は、運動神経と副交感神経の2つがある。
運動神経は、眼瞼を挙げて眼を開く上眼瞼挙筋の運動、上直筋.下直筋.内側直筋.下斜筋の眼球を動かす4つの筋の機能を調節する。
副交感神経は、毛様体筋によりレンズ(水晶体)の厚みを調節してピントを合わせる、瞳孔括約筋により瞳孔を収縮させてレンズに入る光の量を調節する運動を司る。
麻痺の症状
動眼神経の運動神経支配である外眼筋麻痺を引き起こす。
1.眼瞼下垂
眼瞼下垂は、まぶたが垂れ下がる事で目の半分以上が覆い被さり、視界が狭くなることがある。
まぶたを上げる筋肉には上眼瞼挙筋とミュラー筋という筋肉がある。
上眼瞼挙筋は動眼神経の支配を受けているため、動眼神経が麻痺すると、まぶたが上がらなくなる。
もう一つはミュラー筋という筋肉で、自律神経の支配を受けている。この補助的な役割を持つミュラー筋に過度な負担がかかると自律神経の状態も乱れやすい。
2.眼球運動障害
動眼神経麻痺がおこると、眼球を動かす4つの筋肉(上直筋.下直筋.内側直筋.下斜筋)に異常おこり、眼球運動障害がおきる。
正面をみた時に侵された側の眼は外側へ向き、複視(物が二重に見える)の症状が起こる。
3.散瞳
通常、瞳孔は光の下では収縮するが、動眼神経麻痺がおこると眩しい光の下でも瞳孔は広がる(瞳孔散大)
なぜ起きる?
五臓六腑の「肝」は目に開竅するといわれていている。
腎精と肝血は相互に滋養する関係であり、目は精血の滋養に依存している、と考えるため、五臓六腑の「肝.腎」の病症と関係する。
「肝血虚」「腎精不足」がおきると目を滋養する事が出来なくなり目に影響がでるとされる。
肝血が不足すると視覚の異常や運動系の異常.運動神経系の調節に関係があると考えられている。
「肝」は精神の安定.自律神経系を介した機能調節もおこなっており「肝」の機能低下は動眼神経の副交感神経にも影響を及ぼすと考えられる。
東洋医学では…
主に血流障害が原因。
糖尿病に罹患されている方に多く見られる。
動眼神経を栄養する動脈に変化が出やすく血虚になりやすい為に麻痺がおこるとされる。
瞳孔は正常な事が多い。
治療は血糖のコントロールも必要になる。
外科的疾患(動脈瘤.脳腫瘍)などでも動眼神経の圧迫が原因で麻痺が出る。
その場合は散瞳を認める事が多い。
通常、動眼神経麻痺は後天性ですが、稀に先天性の動眼神経麻痺にある。
片側が多いが、両眼性動眼神経麻痺もある。
鍼灸治療
動眼神経麻痺で複視の症状が出ている方に対して鍼通電療法を行っている。
目の周りの筋肉に鍼を刺して刺して電気の刺激を加えていくことで強制的に筋肉を動かして筋肉が正常に機能するように働きかけていく。
また神経は電気信号によって感覚や動作の指令などが伝わっていくため電気刺激を行うことにより神経にも刺激を与えて神経が正常に機能するようにアプローチしていく。
「肝」に関する経穴を用いて肝血を補うことや肝気の巡りを良くしていき、目の周辺の経穴に鍼を刺して微電流を流すことにより目の血行状態を良くして、目の周辺の筋肉に刺激を与えて麻痺の解消を促す。
生活習慣の改善
糖尿病や高血圧が原因で神経への血流不足が考えられる方は生活習慣の改善を推奨する。
1.適切な食事量
2.ナトリウム(塩分)制限
6g未満/1日
3.野菜.果物の積極的な摂取
カリウムが多い野菜や果物はナトリウム(血圧上昇)に対して拮抗に働き降圧効果がある。
4.適正体重の維持
BMI25未満目標
5.運動(有酸素運動)
軽いジョギングや速歩など。
6.禁煙
長期喫煙は動脈硬化となり高血圧の元になる。
7.適度な飲酒
ビール中ビン1本または日本酒1合程度。
8.ストレス発散
自分にあった発散方法を見つける