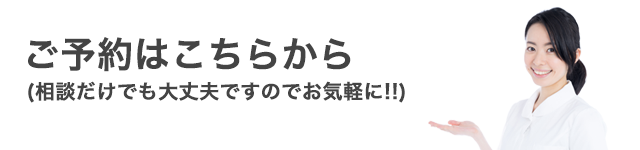寝違えとは
寝違えとは、眠りから覚めた時に、首から肩にかけて痛みが生じることです。正式名称は「急性疼痛性頸部拘縮(きゅうせいとうつうせいけいぶこうしゅく)」といいます。首や肩周辺の筋肉が炎症し軽い肉離れを起こしている状態です。
筋肉痛のような痛みが生じ、結合織炎の一種とも考えられます。痛みの原因が、筋肉自体の炎症や損傷により起こるのではなく、神経系や循環系の変化が起因しているということを結合織炎と呼びます。
寝違えの原因
就寝中に無理な姿勢が続くことによって、筋肉の一部が阻血状態に陥り、その固まった筋肉が起床時に急に動かすことによって寝違えが発症します。
また、体が過度な疲労や、泥酔状態になり、寝返りを打つ回数が少ないことも、筋肉が阻血状態が陥りやすくなります。
前の日に、激しいスポーツや労働をすることによって一部の筋肉が痙攣する「こむら返り」も寝違えを引き起こすともされています。特に、上肢の使い過ぎが大きな原因として挙げられます。
頭部の重さは約5kgです。この頭を支える枕も、寝違えと深く関係しています。頭部から首にかけて、S字カーブを描いています。そのS字カーブを崩さない、自分に合った枕を選ぶことも大切です。
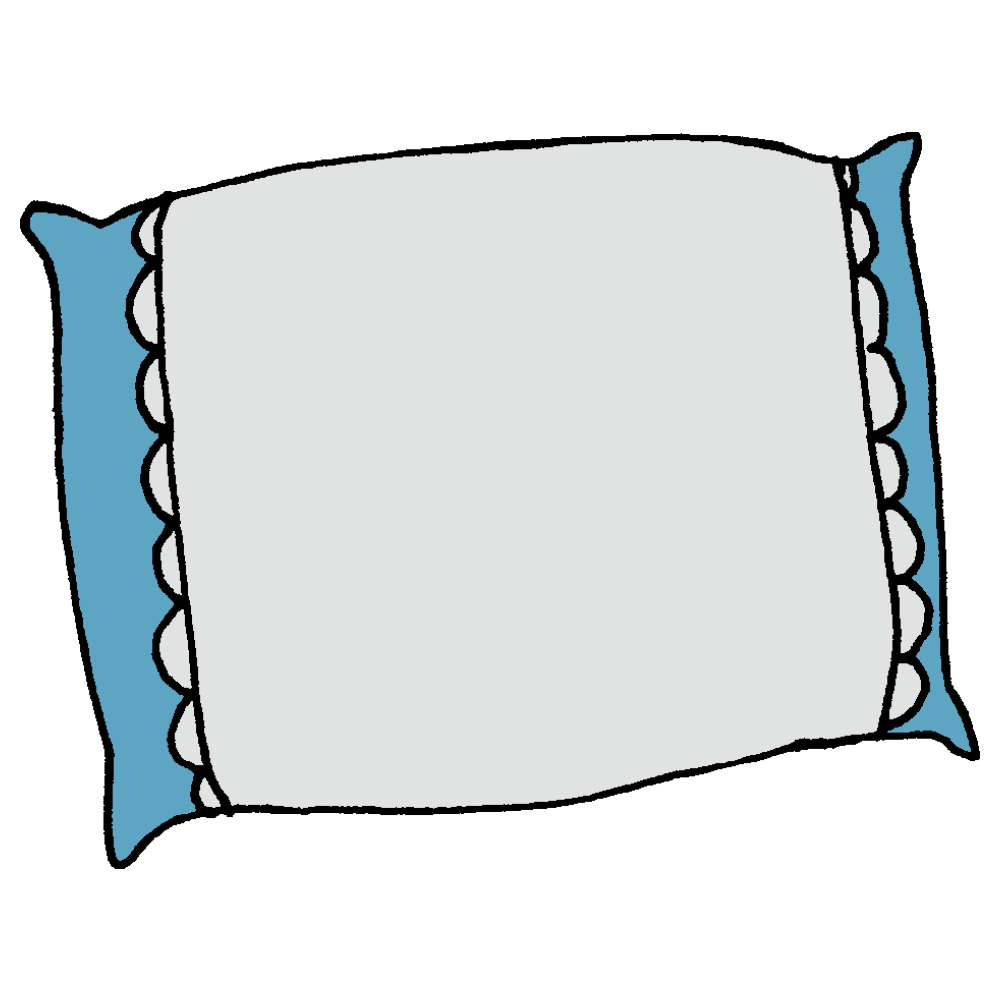
その他にも、運動不足や、精神的なストレスも大きく影響していると言われています。過度なストレスにより人の体は緊張状態になります。この緊張状態は血流の悪化を引き起こし、筋肉が硬くなり、寝違えを起こしやすくなります。
通常、ほとんどの寝違えは1週間程度で徐々に治っていきますが、痛みが長引く、痛みがひどくなっていく場合はすぐに専門医の受診を心がけましょう。
東洋医学と鍼灸
寝違えは東洋医学的に「落枕(らくちん)」と呼びます。枕から頭がずれて落ちることを表しています。ツボとしても存在し、手の甲側にあり、中指と人差し指の付け根の間にあります。
また、「風寒の邪」によって発症すると言われており、冷えによって筋肉が硬くなり、動きが悪くなることにより様々なトラブルが出ることを東洋医学では「風寒の邪」と呼びます。
また、痛い所の周辺の筋肉が硬くなっていることを「気結(きけつ)」と呼び、気の流れが滞っていることを指します。
鍼灸では患部のみならず、全身の血流を促進する施術を行います。

寝違えを予防するには
スポーツをした後や重労働をした後、パソコンやスマートフォン、デスクワークなどで長時間同じ姿勢をとり続けた後には、ストレッチをして体をほぐし、疲れを溜めないようにすることが大切です。背伸び、前屈、首を前後左右に回すなど、簡単なものから習慣づけるようにします。
また、就寝時の冷たい空気により、首周りの血流が悪くなります。これからの時期は冷房など使用により、体が冷えることが多くなります。適切な設定温度で使用しましょう。体が冷えた時には、湯船に浸かり、体を温めると良いでしょう。

万が一寝違えてしまったときは、無理に動かず安静にしてください。
寝違えの痛み緩和の施術はもちろん、寝違えをしないよう身体のバランスを整える施術を行っています。是非ご相談ください。